「おもちゃ、ちゃんと片付けて!」
毎日のようにそう声をかけているのに、子どもはなかなか動いてくれない…。
以前のわが家では、片付けのたびに小さなバトルが繰り返されていました。
こんにちは、30代主婦のゆきです。
ある日ふと、「もしかして、片付けって子どもにとって“楽しくない時間”なんじゃない?」と気づいたんです。
大人にとっては「やるべきこと」でも、子どもからすれば「何が正解かわからない、つまらない作業」なのかもしれないと。
そこで思いきって、“片付けを遊びにしてみよう”と始めたのが、夜5分だけの片付けゲーム。
時間も短く、ルールもシンプル。
それなのに、子どもが驚くほどスムーズに動いてくれて、私自身のイライラも激減しました。
この記事では、わが家でうまくいった片付けゲームの実例や、子どものやる気を引き出すコツをご紹介します。
片付けがちょっと楽しくなる「夜の5分習慣」、今日から試してみませんか?
①子どもが片付けを嫌がるのはなぜ?

「片付け=つまらないこと」というイメージがあるから
以前の私は、「なんで片付けできないの!?」とイライラしっぱなし。
でもあるとき、「そもそも楽しくないし、何をすればいいか分からないんだ」と気づいてから、親子の関係が少し変わりました。
子どもにとって片付けは、「遊びの終わり=がっかりの時間」。
さらに「ちゃんと片付けて」と言われても、どこにどう片付けるのかが分からなければ、やる気も起きません。
楽しい時間を中断させられるうえに、大人から「早く片付けなさい」と言われると、ますます「イヤなもの」という印象が強まってしまうんですよね。
“どこに何をしまうか”が子どもにとってわかりにくい
「片付けて」と言っても、子どもにとっては“どこに”“どう”しまえばいいのかがあいまいなことが多いです。
わが家では、まず“全部このカゴに入れればOK”というざっくりルールに。
場所をはっきりさせることで、少しずつ「片付け=できること」に変わっていきました。
「わかりやすく伝えるだけで、こんなに違うんだ」と私自身の声かけにも変化が。
イライラが少し減ったのを、はっきりと実感しました。
大人の「ちゃんと片付けて」が子どもには抽象的すぎる
大人にとっては当たり前の言葉も、子どもには具体性がないと伝わりません。
たとえば「ちゃんと片付けて」と言われても、「どこに置けば“ちゃんと”なのか」が分からないと、やる気が出ません。
「このカゴにブロックを入れてね」と具体的に伝えることで、子どもの理解もスムーズになりました。
②ゲーム感覚にすると片付けは“楽しい時間”に変わる

「競争」「ごほうび」など、子どものやる気スイッチを入れる
「片付け=楽しくない」をひっくり返すには、“遊びに変える”のが一番。
「早く片付けなさい!」から「ママと競争しよう!」に変えたら、子どもの表情がパッと明るくなったんです。
「ママより早くおもちゃしまえるかな?」「何個入れたらごほうびがあるよ!」と声をかけると、子どもがノリノリで参加してくれるようになりました。
“やらされる作業”を“楽しい時間”へ。
我が家では、
- 「タイマーが鳴るまでに何個しまえるかな?」
- 「赤いおもちゃを探して片付けてみよう」
- 「ビンゴがそろったらごほうび!」
そんな声かけをするだけで、片付けへのやる気がグンとアップ!
達成感やちょっとした報酬があると、子どもは目を輝かせて動いてくれます。
「5分だけ」と決めることでハードルが下がる
「長い時間片付けさせられる」と思うと、やる気がなくなるのは当然です。
ポイントは「5分だけ」という時間設定。
「長い時間やらされる」と思うと気が重くなりますが、「5分だけならやってみようかな」と子どもも前向きに取り組めます。
タイマーを使って「ピピッとなったらおしまいだよ」と伝えると、子どももゲーム感覚で取り組みやすくなります。
親も一緒にやると“遊び感覚”が増して楽しい
親が「片付けしなさい」と命令するのではなく、一緒にやることで“遊びの延長”になります。
「ママもやるよ!競争しよう!」と声をかけると、うちの子もすぐに参加してくれます。
私自身も、「一緒に笑って終われた」「今日も怒らずにすんだ」という小さな変化がうれしくて。
毎日の終わり方が、少しずつ穏やかになりました。
“一緒に楽しい時間を過ごせた”と感じられると、親子のコミュニケーションも増えて一石二鳥ですね。
③我が家で成功した“夜5分片付けゲーム”3つ

「タイマー競争」ゲーム
タイマーを5分にセットして、「音が鳴るまでに何個おもちゃをしまえるかな?」と競争するだけのシンプルなルール。
子どもは“カウントダウン”にワクワクしながら夢中で片付けてくれます。
終わったあとに「すごい!30個もできたね!」と数を一緒に数えると、さらに満足感がアップします。
「色別お片付け」ゲーム
「赤いおもちゃを探してカゴに入れてみよう!」など、色をテーマにした片付けゲームもおすすめです。
遊びの要素が強くなるので、「片付けしてる」という感覚が薄れ、楽しく続けやすいです。
我が家では、お片付けカードを引いてスタートし、まるで遊びの続きのように取り組んでいます。
「お片付けビンゴ」ゲーム
マス目に「おもちゃを10個しまう」「本を1冊戻す」などのタスクを書いたビンゴカードを作り、1つクリアするごとにマスを塗っていくゲームです。
ビンゴが揃うとシールをあげるなどの小さなごほうびを用意すると、子どももモチベーションが続きやすくなります。
「片付けた=褒められる・うれしい」体験が増えると、片付け自体への苦手意識もどんどん減っていきます。
「タイマーを使って遊ぶように片付ける」のは、実は大人にも効果的な方法なんです。
子どもだけでなく、自分自身の“片付けのハードル”を下げたい方には、こちらの記事もおすすめです。
④習慣化するコツは“褒める&一緒にやる”こと

「すごい!」「助かったよ」とリアクションを大きめに
子どもは親の反応に敏感です。
「すごいね!助かったよ〜」の一言で、子どもはパッと笑顔に。
親のリアクション次第で、やる気のスイッチが入ることも実感。
大げさに褒めると、自信がついてどんどん前向きにもなってくれました。
「片付けたら喜んでもらえた」という成功体験が、次のやる気につながります。
親も一緒にやって「一緒にできたね!」と共有する喜びを増やす
「一緒にできたね!楽しかったね!」と最後に伝えることで、片付けが“親子の楽しい思い出”になります。
「ちゃんとできたね!」と認められることで、子どもの中に「片付け=自分でもできること」という自信が育っていきます。
ポイントは「片付け=イヤな時間」ではなく「ママと楽しく過ごす時間」に変えること。
そして、「一緒にやったね!」と共有することも大切な時間に。
親がただ指示するのではなく、一緒に動くことで、「片付け=楽しかった思い出」になります。
毎日じゃなくてもOK。「今日はやろうか」と気楽に続ける
「毎日やらなきゃ」と思うと親もプレッシャーを感じますよね。
わが家では「今日はどうする?」「5分だけやる?」と、その日の気分で決めています。
無理なく、でも継続できることが、長く続けるコツだと感じています。
「片付けを続けるコツは、“戻すだけ”の仕組みを作っておくこと」とも言われています。
おもちゃや日用品の収納をもっとラクにしたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。
⑤まとめ|夜5分が“片付け好きな子”を育てる

「片付けなさい」ではなく、「一緒に遊ぼうか」の一言が、子どものやる気を引き出すことに気づけたこと。
それがわが家の片付け時間を大きく変えてくれました。
“夜5分だけ”の片付けゲームは、忙しい日でも取り入れやすく、子どもも親も負担が少ないのが魅力です。
片付けが楽しい思い出になれば、片付けはイヤなことというイメージも自然と薄れていきます。
5分だけでも、親子で一緒に過ごす前向きな時間が生まれる。
それが「片付け=イヤなこと」から、「ちょっと楽しいこと」へと変えてくれるんです。
やがて、「遊んだら戻す」が当たり前の習慣に変わっていくかもしれません。
今日の夜、タイマーをセットして「何個片付けられるかな?」と聞いてみてください。
たった5分が、あなたとお子さんの暮らしを少しやさしく、ちょっと楽しくしてくれるはずです。
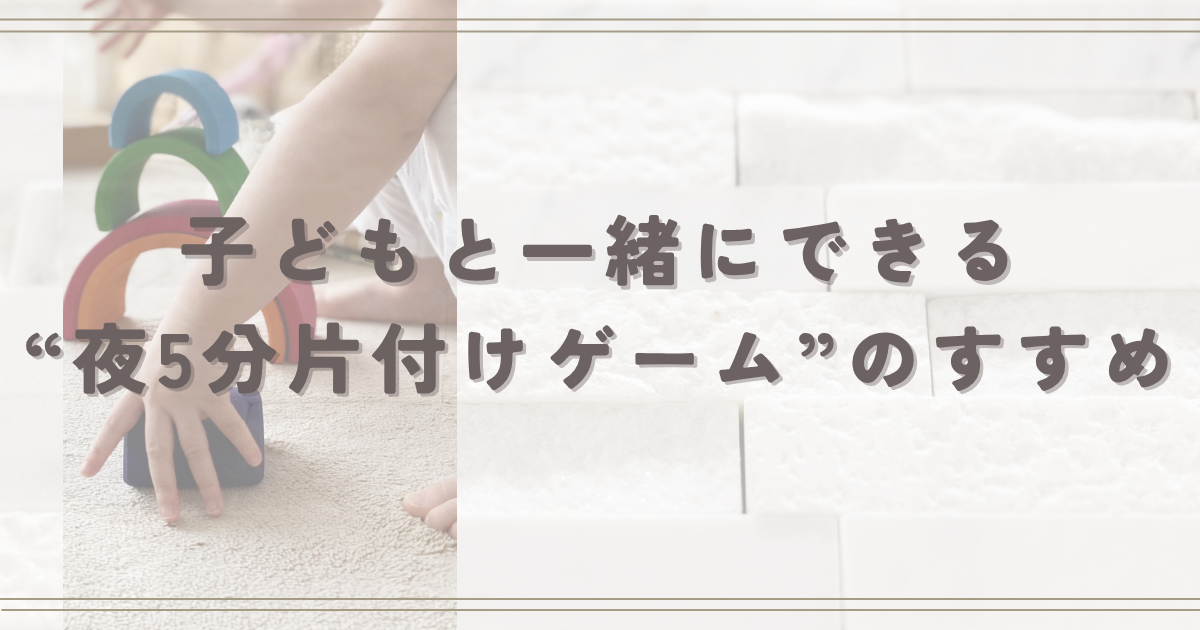
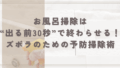
コメント