気がつけばあふれている子ども服。
毎日着せるものなのに、引き出しを開けるたびに「これ、もう着ないのに…」「でも捨てるのはもったいない…」とモヤモヤしていませんか?
こんにちは、30代主婦のゆきです。
子ども服が増えすぎて収納がパンパン、何を着せたらいいか選ぶのもひと苦労…そんな悩みを抱えるママは少なくありません。
我が家も同じで、子供服で溢れかえっていました・・・。
子どもはすぐに成長するから服が増えるのは仕方ない…とあきらめがちですが、実はちょっとしたコツで“ムリなくスッキリ”整理することができます。
ポイントは「がんばらないこと」「完璧を目指さないこと」。
思い出の服はちゃんと残しつつ、「今着る服だけ」を気持ちよく使える状態にすれば、朝の支度もラクになって気分も軽やかになりますよ。
今回は、「子ども服が多すぎる…」と感じたときに、ムリなく減らして整理するためのコツをご紹介します。
どれも今日から取り入れられる簡単な方法ばかりなので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
①なぜ子ども服はこんなに増える?理由を知るだけで心が軽くなる

成長が早いからこそ「サイズアウト予備軍」が増える
子どもは本当にあっという間に成長します。
昨日まではぴったりだったのに、今朝着せたら「パツパツ…」なんてことも珍しくありませんよね。
特に乳幼児期は1シーズンでサイズが変わってしまうこともあるため、頻繁に買い足す必要が出てきます。
その一方で、「まだ着られるかも」と思って取っておいた服が、気づけばサイズアウトしていた…なんてケースも。
こうして“今は着ないけどまだ捨てられない”服=サイズアウト予備軍がどんどん溜まっていきます。
また、シーズンの途中で気温が上下すると、薄手や厚手を買い足す場面も増えます。
こうした“予備”のつもりで買った服も意外と着る機会が少なく、そのままタンスの肥やしに。
サイズアウト予備軍は、放っておくとあっという間に「服が多すぎる!」状態の原因になります。
「かわいいから買っちゃう!」親の気持ちが原因だったりする
子ども服って本当にかわいいですよね。
ちいさなサイズ、パステルカラー、ふわふわの素材…。
買い物中に「これ絶対似合いそう!」「プチプラだからいいよね」と、つい手が伸びてしまうことはありませんか?
特にママにとって、子ども服を選ぶことはちょっとした癒しや楽しみにもなっているもの。
ですがその“つい買い”が積み重なると、気づけば出番のない服だらけになってしまいます。
また、セール品や福袋なども曲者。
「安いし、着られそうだから」と勢いで買ったものの、結局ほとんど着せなかったり・・・。
自分の「買いすぎる傾向」に気づくだけでも、今後のお買い物の選び方が変わります。
もらいもの・おさがりの「ありがたいけど困る」問題
親戚やママ友からのおさがりは、経済的にもありがたい存在。
ただ、「とりあえず受け取っておくけど、実は好みじゃない」「季節がズレてて使えなかった」という経験はありませんか?
サイズや好み、使用感などが合わないと、タンスに眠るだけになってしまうことも少なくありません。
また、お祝いなどでもらった新品の服も「もったいなくて着られない」としまい込んでしまうことも。
いただいたものだから手放しづらい…そんな“ありがたいけど困る”服がたくさんある場合、心の中で整理がつかずどんどん増えてしまいますよね。
「増える理由」を知ると、「減らしていいんだ」と思える
「なんでこんなに服があるんだろう?」と思ったとき、まずは“増える理由”を知ることが大切です。
成長の早さ、親の心理、まわりからのもらい物…。
どれも悪気があるわけではなく、自然なことなんです。
理由を明確にすれば、「これはもう手放していいんだ」と自分を責めることなく前に進めるようになります。
子ども服は特別なもの。
だからこそ、気持ちの整理がつくプロセスを踏むことがとても大切です。
②減らす基準は“今着ているかどうか”だけでOK

「1か月着てない服=ほぼ出番なし」と考える
「まだキレイだし」「いつか着るかも」——その“いつか”は、意外とやってきません。
特に子ども服は、季節や成長に左右されるスピードが速いため、「今」着ていない服の多くは、結局そのまま使われずに終わってしまうことがほとんど。
そこでおすすめなのが、「1か月着てない服は、今後も着ない」と判断するシンプルな基準。
1か月間様子を見て、出番がなかった服は、まず一度“候補外”にしてみるだけでも気持ちがスッキリしますよ。
たとえば、子どもの衣類に小さなタグを付けて、「前回着た日付」を記録しておくのも◎。
視覚的に管理できると、思い切りやすくなりますよ。
「今着せたいか?」を自分に質問してみる
減らすかどうかの判断に迷ったときは、「これ、今のわが子に着せたい?」と自分に問いかけてみてください。
サイズが合っていても、「ちょっと色あせてきたな」「あまり似合わない気がする」と思うなら、その服はすでに“お気に入りではない”サイン。
子どもの写真を見返して、「これ着てたとき、かわいかったな」と思える服だけ残すのも一つの基準です。
服は消耗品ですが、思い出を一緒に過ごす“パートナー”のような存在。
今、子どもが心地よく着られるか?という視点で選んでみてくださいね。
思い出の服は「保留OK」。でも一軍とは分ける
「これは思い出が詰まっていて捨てられない…」という服、ありますよね。
初めて歩いた日や、入園式など、特別な時間を共に過ごした服は、簡単に手放せないもの。
でも、だからといって“よく着る服”と同じ場所に入れてしまうと、収納が圧迫されて日々の服選びが大変になります。
そんなときは、「保留ボックス」を用意するのがおすすめ。
思い出の服は、普段使いの引き出しではなく、クローゼットの上段や別のケースにまとめて保管。
目に入る場所から一度離すことで、整理がしやすくなりますよ。
さらに、「定期的に見直す」習慣をつけると、「あれ?やっぱりこれ、もう手放せるかも」と気持ちの変化が起きることも。
無理に捨てなくていい、でも“いったん分ける”というステップがとても大切です。
③季節ごとに“定員制”にする

引き出し1つ分=トップス〇枚、ボトムス〇枚と決める
子ども服が増えすぎてしまう理由のひとつは、「どれだけ持っていていいのか」が曖昧なこと。そこでおすすめなのが、“定員制”という考え方。
たとえば、「春夏はトップス8枚・ボトムス5枚」と枚数を決めて、その範囲内でやりくりするスタイル。
ちょうど引き出し1段に入るくらいが目安です。
視覚的に「これ以上は入らない」とわかれば、自然と増えすぎを防げます。
子どもは汚す頻度も高いため、洗い替えも含めて「少し余裕を持つ」ことも忘れずに。
ただし、数を決めることで「これはもう出番が少ないから手放してもいいかな」と見直すきっかけにもなります。
最初は少し勇気がいりますが、私も実際に“必要な枚数”で生活してみると、「意外とこれで足りる」と感じられるようになりました。
「入らないなら1枚手放す」のルールにする
定員制を守るためには、「新しい服を買ったら1枚手放す」というルールを作るのがポイント。
これは“1in1out(ワンインワンアウト)”と呼ばれ、モノを増やさないための基本ルールでもあります。
子どもと一緒に「どれを卒業しようか?」と相談しながら決めるのもおすすめ。
自分で選ばせることで、モノを大切にする気持ちも育ちます。
さらに、「シーズンごとに見直す日」をカレンダーに入れておくと、定期的に整理が習慣になります。
衣替えのタイミングや長期休み前など、区切りのタイミングを活用すると、スムーズに行動できますよ。
定員制にすると、選びやすく着せやすいメリットも
枚数を減らすと、「朝の服選びがラクになった!」と感じます。
選択肢が少ないことで迷う時間が減り、パッと決められる。
結果として、子どももママも朝のストレスが軽減されます。
また、よく着る服だけが並ぶので、収納もスッキリして見た目も気持ちいい。
引き出しの中がゴチャゴチャしていると、それだけでイライラしがちですが、定員制で見える化することで、使い勝手が一気によくなります。
服が少ないからこそ、「あの服また着たい!」と子どももお気に入りを大切にするようになりますし、結果的に“着倒す”ことで無駄も減ります。
「たくさん持っている=安心」ではなく、「必要な分だけある=快適」という考え方にシフトしていくと、服選びも暮らしももっと楽になりますよ。
写真に撮って思い出を残すのもアリ
「思い出の服が多すぎて選べない…」という場合は、写真に撮って“デジタル保存”するのも有効な方法です。
子どもがその服を着ていたときの写真はもちろん、服だけをキレイに広げて撮影するのもOK。
スマホで簡単に記録できるので、場所を取らず、後から見返すこともできます。
おすすめは、思い出の服ごとにエピソードを書いたメモを添えること。
「2歳の誕生日に着た服」「初めての遠足の日のTシャツ」など、ストーリーと一緒に記録しておくと、写真がより一層価値あるものになります。
デジタルアルバムにまとめたり、スクラップブックを作ったりすれば、子どもが成長したときのプレゼントにもなりますね。
服そのものは手放しても、「記憶」としてちゃんと残すことができる。
それだけで、整理への罪悪感は軽くなります。
「特別な服だけ」に絞ると手放す基準が明確になる
保管スペースには限りがあるからこそ、「どこまで残すか」の基準を決めておくと整理しやすくなります。
たとえば、「記念日や行事で着た服だけ残す」「親子の写真にたくさん写っている服だけ残す」など、“自分なりのルール”を設けると選びやすくなります。
迷ったら、「その服を見て何かエピソードが思い浮かぶか?」を自分に問いかけてみてください。
単に可愛かったから残しているだけの服より、「この服、あのとき泥だらけにして遊んだなぁ」と思い出せる服のほうが、“特別な存在”であることがわかります。
たくさん残すのではなく、「本当に大切なものを、大切に扱う」ことが整理の目的。
手放すことは、忘れることではありません。
心に残すことを大切にしながら、空間にもゆとりをつくっていけるといいですね。
④譲る・売る・寄付するで“次に着てくれる人”へ

子ども服の整理で、「もう着ない」と判断できても、捨てるのはなんだか気が引ける…。
そんなときこそ、“次に着てくれる人”へ届ける方法を考えてみましょう。
服にもう一度、役目を与えることができると、気持ちもぐんと軽くなります。
ママ友や親戚に「使えそうならどうぞ」と声をかける
いちばん手軽で、気持ち的にもハードルが低いのが、身近な人に譲る方法です。
「サイズ80くらいの服がいろいろあるんだけど、使いそうならどう?」と軽く声をかけるだけで、意外と喜んで受け取ってくれることもあります。
ママ同士のあいだでは、「子ども服ってすぐサイズアウトするよね〜」という共通の悩みもあるので、お互いに譲り合うのはごく自然な流れ。
気を遣いすぎず、「使わなかったら気にせず処分してね」と一言添えると、相手も受け取りやすくなります。
また、親戚や近所の子どもがいる家庭に聞いてみるのもひとつ。
人づてで“欲しい人”に服が巡っていくこともあるので、まずは一声かけてみる価値は大です。
フリマアプリ・リサイクルショップならお小遣いにもなる
ちょっとした手間をかけてもいい場合は、フリマアプリやリサイクルショップの活用がおすすめです。
特に人気ブランドの子ども服や、状態の良いアイテムはフリマアプリ(例:メルカリ、ラクマ)で出品するとすぐに売れることも。
「可愛かったから少しでも活かしてほしい」「次の誰かが大切に使ってくれるならうれしい」という気持ちがあるとき、こうした方法はぴったりです。
一方で、「撮影や発送が面倒…」という方には、近所のリサイクルショップ(例:セカンドストリート、トレジャーファクトリーなど)にまとめて持ち込む方法も。
買取金額は高くはないかもしれませんが、すぐに処分できて、ちょっとしたお小遣いにもなるのは大きなメリットです。
時間があるときに「これは売る」「これは譲る」とあらかじめ分けておくと、整理作業がスムーズになりますよ。
寄付なら「誰かの役に立つ」と思えて気持ちが軽くなる
もう一つの選択肢が、寄付という形で手放す方法です。
たとえば、子ども支援団体やNPO、地域の福祉団体、海外支援のプログラムなど、寄付を受け付けているところは意外と多くあります。
服を段ボールにまとめて送るだけの団体もあれば、地元の自治体や教会が“子育て応援プロジェクト”として受け入れているケースもあります。
寄付のよいところは、「誰かの役に立っている」と実感できること。
単に「捨てる」のではなく、「次に必要としている誰かに届く」ことで、服の価値がちゃんと生きていくのです。
さらに、子どもにも「この服、誰かがまた使ってくれるんだよ」と話してあげると、ものを大切にする心や人とのつながりを自然と育むきっかけにもなります。
「手放す」=「終わり」ではなく、「次へつなぐ」こと。
大切に着せてきた服たちを、次の人へバトンタッチすることで、服も自分も心から納得して前に進めますよ。
服が減ると片付けやすくなるだけでなく、掃除もぐっとラクになります。
👉 掃除機を出すのが面倒…でも床がキレイになる“手抜き掃除”アイデア5選
こちらでは、掃除機を使わなくても床が整う簡単な方法を紹介しています。
“片付けやすい部屋づくり”の次のステップとして、ぜひチェックしてみてくださいね。
⑤まとめ:子ども服は「手放すことで、毎日がラクになる」

子ども服を減らす=捨てる、ではありません。
今の暮らしに合った枚数に見直し、「着せたい服だけ」にすることで、日々の育児がグッとラクになります。
「多すぎてどうしていいかわからない」と悩む前に、まずは“なぜ増えるのか”を知ることから始めてみましょう。
感情に寄り添いながら、ムリなく整理できるルールを取り入れることで、片付けのハードルが一気に下がります。
お気に入りや思い出の服は大切に残しつつ、「今の子どもに合う服」をスッと選べる暮らしを。少しずつでも、きっと気持ちも空間もスッキリします。
タンスいっぱいの服を一気に減らすのは大変ですが、“1枚だけ手放す”ことからなら、今日すぐに始められますよ。
子ども服を整理すると、片付けがぐっとラクになりますが、子ども自身が片付けてくれない…という悩みもありますよね。
そんなときは、
👉 子どもが片付けてくれない…イライラしない工夫と“自然に続く”習慣3つ
こちらの記事も参考になります。
「怒らなくても自然に片付けが続くコツ」をまとめているので、服の整理とあわせて実践すると、毎日の片付けがもっとラクになりますよ。
まずは、どの服から手をつけてみますか?
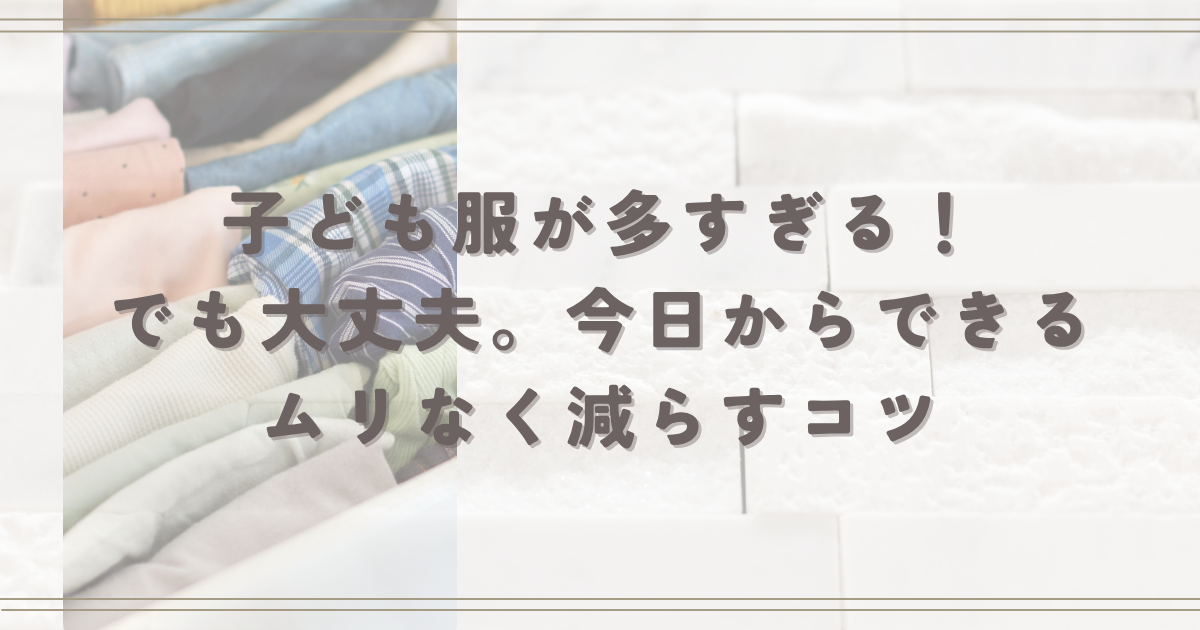
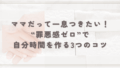
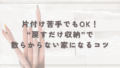
コメント