「もったいなくて捨てられない」「いつか使うかもしれない」「思い出があって手放せない」——そう思って、気づけば物がどんどん増えていませんか?
こんにちは、30代主婦のゆきです。
3歳の娘と暮らす我が家では、日々の生活の中でどんどんモノが増えていき、収納もパンパン、床にも物があふれてしまうことがよくありました。
「片付けたいけど、何をどう捨てればいいのか分からない」と、ずっと悩んでいたんです。
でも、いきなり「断捨離しよう!」と意気込むのは、私にはムリでした。
そんな私でも、気持ちをラクにしながら少しずつ物を手放せるようになった3つのステップがあります。
今回は、捨てられなかった私が実際に実践した「手放す習慣」と、そこから得られた気持ちや暮らしの変化についてご紹介します。
① なぜ私は“捨てられない人”だったのか?気づいた3つの理由

1. 「いつか使うかも」が口ぐせだった
私が捨てられなかった一番の理由は、「これ、いつか使うかもしれない」と思ってしまうことでした。
特に育児グッズやキッチン用品、趣味の材料などは、「使わないけど高かったし」「誰かにあげられるかも」と思って、ずっとしまい込んでいました。
でも、現実にはその“いつか”はほとんど来ないんですよね。
保管スペースにも限りがあるのに、「まだ使える」と思って取っておくと、どんどん物が増えていきます。
私は気づかないうちに、「使うかどうか」ではなく「捨てられない理由」を探していたように思います。
2. 思い出が詰まっているものは罪悪感が大きい
子どもが初めて描いた絵、旅行先で買ったお土産、友人からもらったプレゼント…。
そういった“思い出のあるもの”は、手に取るたびに感情が揺れて、なかなか処分できませんでした。
「捨てたら思い出まで消えてしまう気がする」と感じて、ずっと引き出しの奥や棚の中にしまっていたのです。
でも、思い出は物ではなく心の中に残るもの。
無理に全部捨てなくてもいいし、写真に残すなどの方法で、気持ちを整理しながら手放すことができると気づきました。
3. 「もったいない精神」と育ちの影響
私は「もったいない」が口ぐせの家庭で育ちました。
母も祖母も、物をとても大切にしていて、「壊れるまで使うのが当たり前」という価値観が根づいていたんです。
そのため、まだ使える物を捨てることに大きな抵抗がありました。
ただ、その“もったいない精神”が、自分を苦しめてしまっていたことにも気づきました。
使っていない物にスペースを取られたり、探し物が見つからなかったり…。
そんな無駄な時間やストレスこそが、実は「もったいない」ことだったんです。
② いきなり断捨離はムリだった。まずは「分けること」から始めた
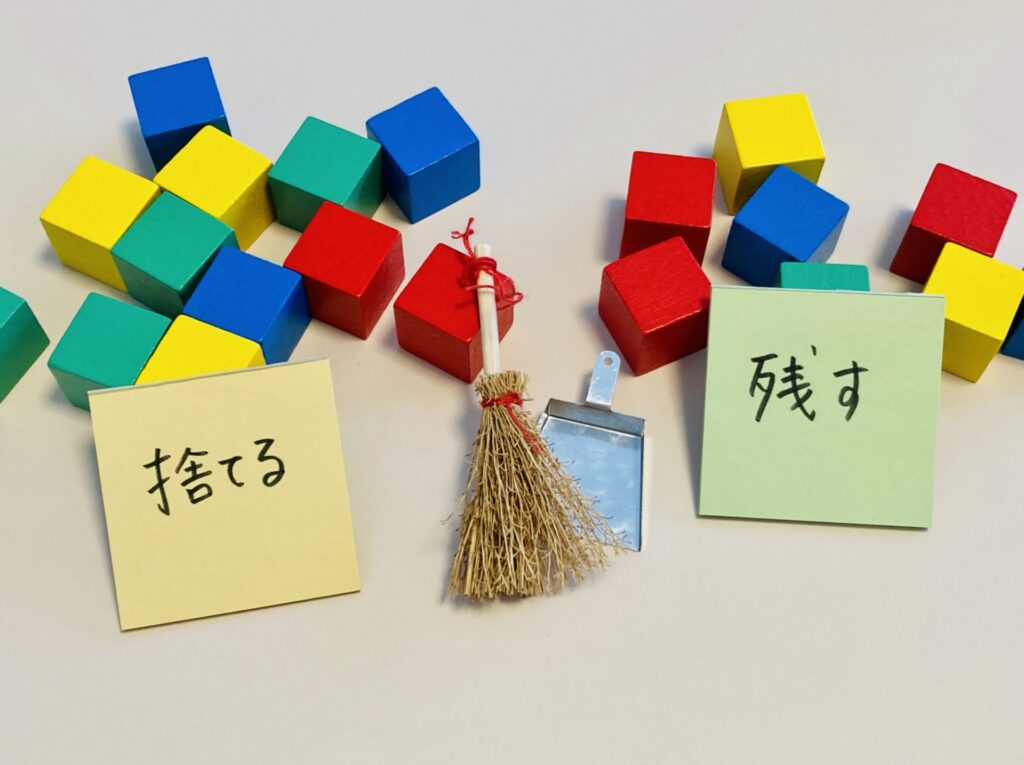
「捨てるのが苦手なら、まず“捨てないで済むこと”から始めよう」と思った私が取り入れたのが、“分けること”でした。
いきなりゴミ袋を持って部屋を回るのではなく、とにかく「一度仕分けしてみる」という方法です。
「とりあえず残す・迷う・手放す」に仕分け
まずは引き出しや棚の中身を全部出して、「とりあえず残す」「迷う」「手放す」の3つに分けることからスタート。
捨てると決められないものは「迷う」に入れてOK。
この“グレーゾーン”があることで、気持ちがぐっとラクになります。
実際、「迷う箱」に入れた物の多くは、数日〜数週間経つと「あれ、なくても困らなかったな」と思えて自然に手放せました。
「今日手放さなくていい」が安心感につながる
「分けるだけ」と決めることで、変なプレッシャーやストレスがなくなりました。
捨てるのは後からでもいい。
まずは物と向き合うことが第一歩。
その気楽さが、継続するコツだったと思います。
仕分けの作業は、家事の合間や子どもが寝た後などの短い時間にコツコツやるのがおすすめです。
1か所ずつ、気が向いたときだけでも十分。
成功体験が「もっと手放したい」につながる
「これはもう使ってないし、ありがとうって言って手放そう」と自分で納得して捨てられたとき、「私にもできた!」という達成感がありました。
その体験が自信になって、「もう少し減らしてみようかな」という気持ちになったのです。
断捨離という言葉にとらわれず、「まずは分けてみるだけ」でいい。
そう思えたことで、私の“捨てられない”人生が少しずつ動き始めました。
📝「片付けたいけど行動できない…」という方へ
習慣化がうまくいった体験談はこちらの記事で紹介しています。
👉 片付けが苦手で床が見えない…私が変われた5つの小さな習慣
③ 捨てる=失うじゃない。手放すと得られた変化とは?

「捨てること」は、何かを失うことだと思っていました。
でも、実際に手放してみると、むしろたくさんの「余白」や「ゆとり」が生まれたのです。
物理的にスペースができて動きやすくなった
まず感じたのは、家の中が圧倒的に“動きやすくなった”こと。
通路に物が置かれていないだけで、家事や掃除の効率がぐっと上がりました。
娘がつまずいたり、物を落としたりする心配も減り、安心して過ごせる空間になりました。
探し物が減ったことでストレスが激減
物が多いと、どこに何があるかわからなくなって、探し物に時間がかかることが多くありませんか?
私は「どこにしまったっけ?」とイライラすることが日常茶飯事でした。
でも、手放したことで物の定位置が明確になり、自然と探し物の頻度が激減。
朝の支度も、格段にスムーズになりました。
気持ちの面でも「心の余裕」が生まれた
物が少ないと、視界がすっきりして、気持ちも整いやすくなりました。
「片付けなきゃ」という焦りやプレッシャーが減り、気づけば心にも余裕が生まれていたのです。
忙しい毎日の中で、ちょっとだけでも自分の時間が持てたり、家族とゆっくり過ごす気持ちの余裕ができたことは、何よりの変化でした。
捨てる=失うではなく、実は「得られるもの」がたくさんあるんだなと気づけたことが、私にとって大きな収穫でした。
④ やってよかった!私が効果を感じた3つの手放しルール

1. 「1日1個だけ」でもOKルール
「今日はこれを手放そう」と、1日1つだけでも物を減らす意識を持つようにしました。
忙しい日でも「これだけならできそう」と思える気軽さがポイント。
実際、毎日少しずつ手放していくことで、いつの間にか引き出しや棚がすっきりしていきました。
「数が少なくて意味があるの?」と思うかもしれませんが、少しずつ続けることで習慣になりますし、「今日もできた」という満足感がモチベーションにもなります。
2. 「使っていない=今の私には必要ない」ルール
以前は「まだ使える」ことを理由に捨てられなかったのですが、「ここ半年〜1年使ってないなら、今の自分には必要ないかも」と考えるようにしました。
自分のライフスタイルや生活環境はどんどん変わっていくもの。
今の私に合わないものは、潔く手放しても大丈夫。
自分の“今”に焦点を当てて判断することで、気持ちも整理しやすくなりました。
3. 「感謝して手放す」ルール
物に「ありがとう」と声をかけてから手放すようにしています。
「これまで使わせてもらってありがとう」と気持ちを込めることで、罪悪感も軽くなり、前向きな気持ちで手放せるようになりました。
特に思い入れのあるものほど、感情をしっかり整理してからの方が手放しやすいと感じています。
💡合わせて読みたい:
出しっぱなし癖を卒業!床に物がたまらなくなった3つの簡単習慣
→ 物が増えた理由や片付けのハードルを減らす工夫を紹介しています。
⑤ まとめ|完璧じゃなくていい。少しずつ、軽くなる暮らしへ
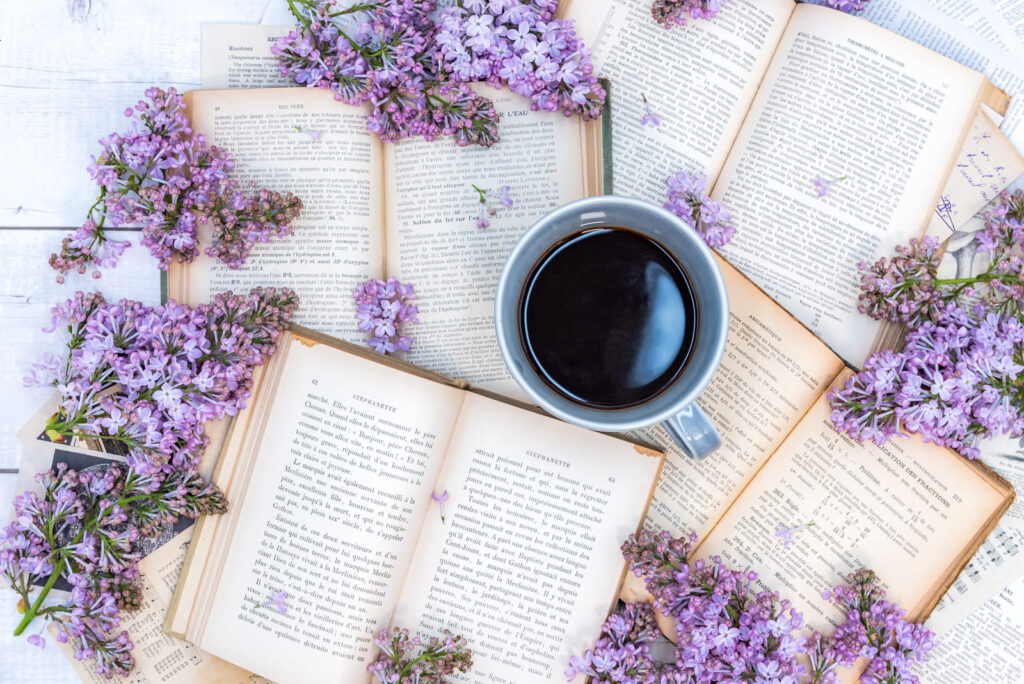
捨てることが苦手だった私が、少しずつ「手放す」ことに前向きになれたのは、自分に合ったやり方とペースを見つけられたからだと思います。
いきなり家中を片付けるのではなく、小さく始めて、「分ける」「迷う」「感謝する」——そんな小さなステップを積み重ねていくことで、心にも家にも余裕が生まれました。
今でも完璧にはできません。
捨てられない日もあるし、また物が増えてしまうこともあります。
でも「またここから整えよう」と思えるようになったことが、何よりの進歩です。
片付けも、手放すことも、きっと“上手な人”になる必要はないと思うのです。
自分にとって心地いい暮らしを少しずつつくっていければ、それで十分。
「捨てられない」と悩む誰かにとって、この体験が少しでも参考になれば嬉しいです。
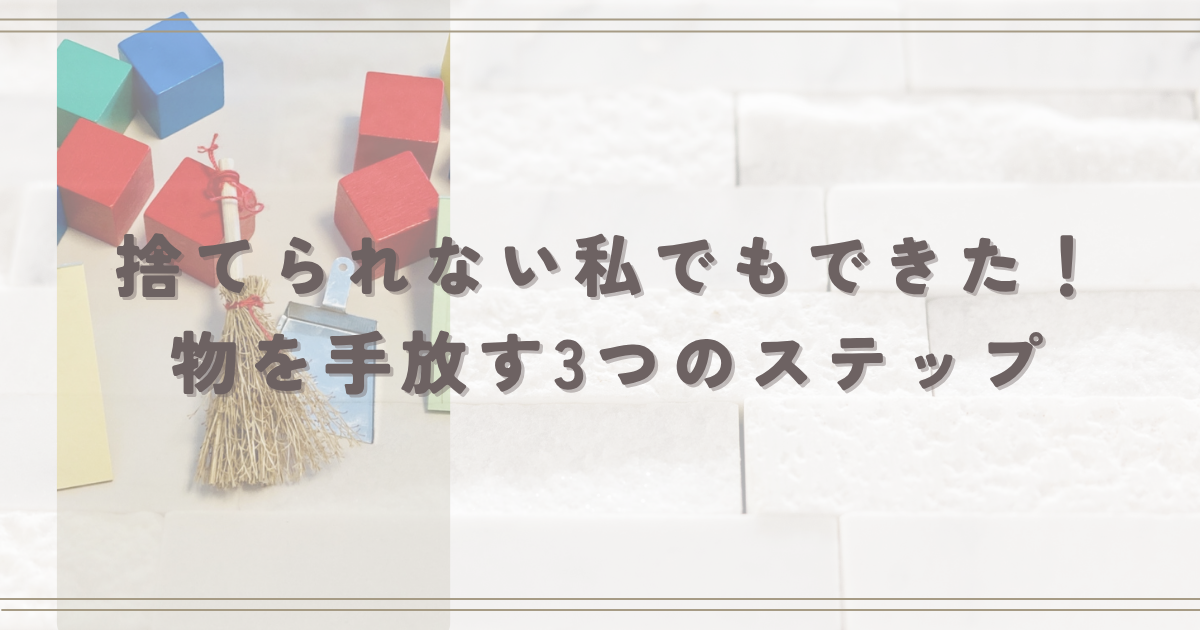
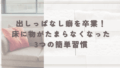
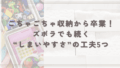
コメント