「これは思い出があるから捨てられない…」
片付けの中でも特にハードルが高いのが、“思い出のモノ”の整理ではないでしょうか。
こんにちは、30代主婦のゆきです。
手紙や写真、子どもの作品や旅行の記念品…。
私自身、娘が初めて描いた絵や、旅行で買った置物を前に「これを捨てたら、あのときの気持ちまで消えてしまう気がして…」と、手が止まったことが何度もありました。
見るたびに当時の気持ちがよみがえって、捨てるなんてとてもできないんですよね・・・。
でも、思い出のモノが増え続けて収納を圧迫すると、日常の暮らしがどんどん窮屈になります。
大切なのは、「思い出を捨てること」ではなく、持ち方を見直し、モノとの付き合い方を変えること。
今回ご紹介するのは、罪悪感を持たずに、無理なく思い出のモノを整理するための3つのステップ。
私自身も実践して、「気持ちがラクになった」と感じた方法です。
手放せなかったモノをどう扱うかに迷っている方へ——やさしく背中を押してくれる整理術を、ぜひ参考にしてください。
①なぜ思い出のモノは捨てられない?感情がブレーキをかける理由

モノそのものより「記憶」が手放せない
思い出のモノが捨てられない理由の多くは、「記憶がそこに詰まっている」と感じるから。
アルバム、手紙、子どもの作品——目にするだけで、そのときの気持ちや出来事が一気によみがえりますよね。
「これを捨てたら、あの思い出まで消えてしまう」。
そんな気持ちになってしまうのです。
私も、娘が初めて描いたアンパンマンの絵を前に「この絵を捨てたら、あの日の感動までなくなってしまう気がする」と、なかなか手放せませんでした。
ほかにも、自分の小学校時代の卒業アルバムなど、「なんとなく手放せないもの」がたくさんありました。
でも、実際によく見てみると、「見返すことはほとんどないけど、捨てたら罪悪感が残りそう」と感じていたのです。
手放すこと=裏切りのように感じてしまう
モノには「くれた人の気持ち」や「そのときの自分の思い」が重なっていて、捨てることでそれを否定するような気がする…。
そんな感覚があるからこそ、手が止まってしまうのは当然のこと。
決して“ズボラ”だからできないわけではありません。
でも、モノの整理は「思い出を捨てる行為」ではありません。
「モノ=思い出」ではない。
モノと心を切り離して考える視点を持つことで、少しずつ“整理する勇気”が持てるようになります。
②ステップ①|「思い出と今使うモノ」を分けるだけでOK

「今の暮らし」に必要なモノはどれ?
まず最初のステップは、“思い出のモノ”と“今使っているモノ”を分けること。
これは、あくまで“仕分け”。
まずは捨てるのではなく「仕分けること」から始めるのです。
たとえば、日常的に使う食器と、旅行先で買ったけど使っていないお皿は、用途も存在意義も異なりますよね。
「これは今使ってる?それとも“思い出”として持ってる?」と問いかけてみるだけでも、今の生活に必要なモノと、思い出のモノが自然と分かれていきます。
箱にまとめて“保留”でもOK
思い出のモノはすぐに手放す必要はありません。
仕分けた思い出のモノは、「とりあえずボックス」を作って、そこにまとめておくのがおすすめです。
無理に今すぐ捨てようとせず、“持ち方”を変えることが目的なので、箱に入れて気持ちの整理を待つ時間も大切です。
数カ月後に見返すと「もう手放しても大丈夫」と思えることも多いんです。
焦って捨てる決断を急がず、気持ちの整理がつくまで“保留”の時間を持つのがポイントです。
③ステップ②|写真に撮って“記憶を残す”という選択肢

モノではなく「記録」で思い出を残す
思い出のモノを手放すことに抵抗がある場合、写真に撮ってデータとして残すのもおすすめの方法です。
たとえば、子どもの工作や手紙、遊んだぬいぐるみ、旅行のおみやげなど、思い出深いけれどスペースをとるアイテムにはぴったり。
スマホやクラウドに保存しておけば、いつでも思い出を見返すことができて、モノ自体を持たなくても思い出は残ります。
アルバムやフォトブックにして形にするのも◎
ただ撮って保存するだけでなく、テーマごとにアルバムを作ると、よりモノ以上に価値のある記録になります。
私は、子どもが作ったり描いたりした作品を1冊にまとめて、フォトブックにしたのですが、スッキリと片付きつつも思い出はしっかり残せて、とても満足しました。
手放す=忘れる、ではなく、「記憶の形を変える」という選択肢を持つことで、罪悪感なく整理が進んでいきます。
④ステップ③|「誰かに渡す」「寄付する」でモノの役目をつなぐ

誰かに使ってもらえる安心感
もう使わないけれど手放しにくい思い出のモノは、「誰かに使ってもらう」ことで気持ちが軽くなることがあります。
たとえば、子どもの小さくなった服や使わなくなったベビー用品など、「これ、まだ使えるのに…」と思うものは、ママ友や親戚に「よかったら使ってね」と譲るのもおすすめ。
“ありがとう”と受け取ってもらえると、「モノが次の場所で役に立つ」と実感できて、手放すことへの迷いも減っていきます。
私も「手放す」ことに前向きになれました。
寄付やリサイクルで「モノの命をつなぐ」
フリマアプリやリサイクルショップを活用するのも一つの手ですが、「利益は気にしないから誰かに使ってほしい」と思うなら、寄付も選択肢のひとつです。
古着回収、子ども支援団体、図書館、地域のバザーなど、モノが役割を終えたあとも誰かの手に渡って活かされるルートは意外とたくさんあります。
「思い出のモノを手放す」ことは、「誰かにバトンを渡す」こと。
整理がぐっとラクになりますよ。
モノの命を次につなぐというやさしい視点で向き合えると、整理も前向きに進められます。
⑤まとめ|モノを減らすことは“思い出を捨てる”ことじゃない

思い出のモノを整理することは、けっして「思い出を消すこと」ではありません。
大切なのは、「モノと心を切り離して考える」という視点を持つこと。
感情が強く結びついているからこそ、一気に手放すのではなく、少しずつ向き合うことが大切です。
今回ご紹介した3つのステップ——
- 思い出と今使うモノを分ける
- 写真に撮って記録を残す
- 誰かに譲ってモノの命をつなぐ
このプロセスを通して、「思い出を守りながら、今の暮らしを整える」ことができます。
「捨てられない」と思っていたモノにも、新しい見方ができたらきっと気持ちがラクになりますよ。
罪悪感なく、モノと向き合えるようになったら、暮らしも心もきっともっと軽やかになります。
あなたなら、まずどのモノから向き合ってみますか?
「写真に撮って残す」「箱に入れて保留する」など、できることから始めてみてください。
その小さな一歩が、きっと気持ちも暮らしも軽くしてくれるはずです。
「思い出のモノ」を整理すると、日常の片付けもラクになります。
「片付け苦手でもOK!“戻すだけ収納”で散らからない家になるコツ」 では、毎日の片付けが無理なく続く仕組みづくりを紹介しています。
「せっかく整理したのにすぐ散らかる…」とお悩みなら、あわせて読んでみてくださいね。
また、
「掃除機を出すのが面倒…でも床がキレイになる“手抜き掃除”アイデア5選」も、スッキリ空間を保つヒントになりますので、あわせて読んでみてくださいね。
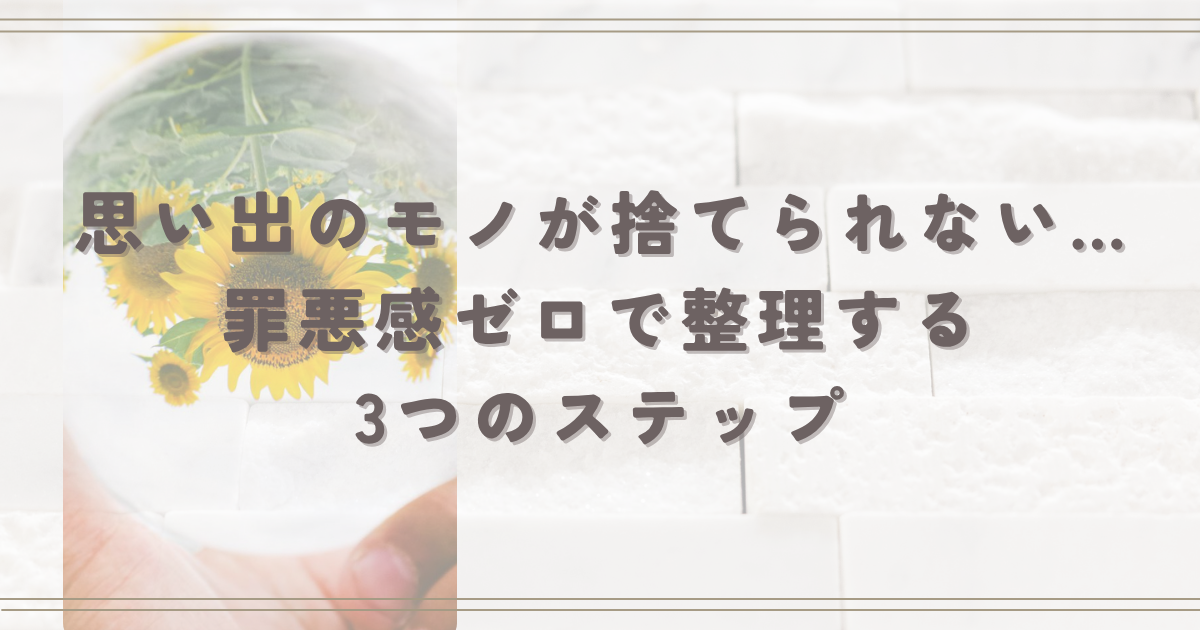
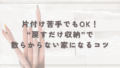
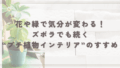
コメント