「おもちゃが多すぎて片付かない…」
育児をしていると、誰もが一度は悩むこの問題。
私もずっと、「片付けても片付けても、すぐごちゃごちゃになる…」というストレスを抱えていました。
こんにちは、30代主婦のゆきです。
気がつけば、誕生日・クリスマス・親戚からのプレゼントなどでおもちゃはどんどん増え続け、収納はパンパン。
「もう遊んでないよね…」と思っても、「これは好きだったやつだから」「いつか使うかも」と思うと、なかなか手放せませんよね。
しかも、子どもに「これいらないでしょ?」と聞いても「全部いる!」と返ってくる…。
捨てづらさ、ありますよね。
この記事では、そんな“おもちゃが多すぎる問題”をムリなく解決していくためのコツを、体験をまじえてご紹介します。
「よし、これならできそう」と思える“減らし方のコツ”を見つけて、暮らしも気持ちもスッキリさせていきましょう!
①なぜ子どものおもちゃはどんどん増えてしまうの?

誕生日・クリスマス・もらいもの…知らない間に増えていく
子どものおもちゃって、気がつくとどんどん増えていますよね。
理由の一つが、「イベントごとにもらう機会が多い」ということ。
誕生日、クリスマス、お年玉代わりのプレゼント。
さらに親戚や友人からのおさがり、幼稚園や保育園のバザーやガチャガチャ景品など、「ちょっとしたもの」が積み重なっていくのです。
こうした贈り物は気持ちがこもっていてうれしい反面、保管スペースがどんどん足りなくなっていくのも現実…。
気づいたら、おもちゃ箱や棚があふれかえっていた、なんて経験ありませんか?
「子どものために」と思ってつい買ってしまう
「これ楽しそう!」「これ遊びながら学べそう!」
つい親のほうが張り切ってしまって、おもちゃを買ってしまうこともあります。
特に知育系や人気キャラクターのおもちゃは、「子どものため」という名目で、自分の満足のために買ってしまうこともありますよね(私もです…!)。
でも、実際に子どもが長く使うおもちゃは限られていたりします。
「せっかく買ったのに、全然遊ばなかった…」と後悔する前に、本当に必要かどうか、冷静に見極めたいところです。
子ども自身が「全部いる」と言う→捨てにくくなる
子どもに「これもう遊んでないよね?」と聞くと、たいてい「まだ使う!」「これ好きなの!」と返ってくる…。
そんなやり取り、よくありますよね。
子どもにとっては、“遊ぶかどうか”だけでなく、「思い出」や「好きなキャラかどうか」も大事な判断基準。
だから、大人から見ると“いらなそう”でも、子どもにとっては“宝物”だったりします。
「全部いる」と言われると、強引に手放すこともできず、片付けが進まなくなってしまうんですよね。
親の「思い出」や「もったいない」が手放せない原因に
そして忘れてはならないのが、「親側の気持ち」。
「このおもちゃで初めて遊んだな」「寝る前にずっとこれで遊んでた」など、思い出がつまっているおもちゃほど、手放しにくくなります。
また、「高かったのに…」「まだ使えるし…」という“もったいない”気持ちも、手放せない原因に。
でも、物があふれていることで日常のストレスが増えるなら、手放すことは“悪いこと”ではありません。
次のステップで、まずは“気持ちを整理する”ところから始めてみましょう。
🧸 「増えすぎたおもちゃを減らす前に…子どもが片付けやすくなる工夫も大事です」
②減らす前にやってよかった“気持ちの整理”

「今、子どもがよく使っているか」を基準にする
おもちゃを減らすとき、基準があいまいだと「どれも捨てられない…」となりがち。
そんなときは、「今、子どもが実際によく使っているか?」を判断軸にするのがおすすめです。
ここ1週間で遊んだか?
毎回スルーされているおもちゃじゃないか?
観察してみると、「実はあまり遊んでいないおもちゃ」がけっこう見つかりますよ。
“今の子どもにとって必要か”で判断すれば、手放しやすくなります。
「減らす=捨てる」ではなく「選ぶ=残す」に言い換える
「捨てる」という言葉って、どうしてもネガティブに感じますよね。
そんなときは、“捨てる”を“選ぶ”に言い換えてみましょう。
「どれを残そうか?」
「お気に入りベスト5を選んでみよう!」
そう伝えるだけで、子どもも前向きに関わってくれるようになります。
選び取る感覚を育てることにもつながり、「物を大切にする気持ち」が自然と芽生えていきます。
「全部はムリでも、まずは5個だけ」など小さくスタート
いきなり大量に手放そうとすると、子どもも親も疲れてしまいます。
そんなときは、「まずは5個だけ選ぼう」と小さく始めるのがポイント。
ゲーム感覚で「これとこれはどっちが好き?」と2択にしていくと、自然におもちゃが絞られていきます。
少しずつ進めていくことで、「減らしても大丈夫」という安心感も育っていきますよ。
捨てられないおもちゃは“保留ボックス”で一時避難もOK
どうしても捨てられない…でも場所はない…。
そんなときは“保留ボックス”を作って、一時的におもちゃを避難させておく方法もおすすめです。
しばらく遊ばなければ「もういらないかも」と自然に思えることも。
逆に、「やっぱりこれはいる!」となったら戻せばいいだけなので、安心して手放せるきっかけになります。
大人のお片付けにも共通しますが、“手放すコツ”を知ると気持ちがぐっとラクになります
③我が家で実践して効果があった5つのコツ
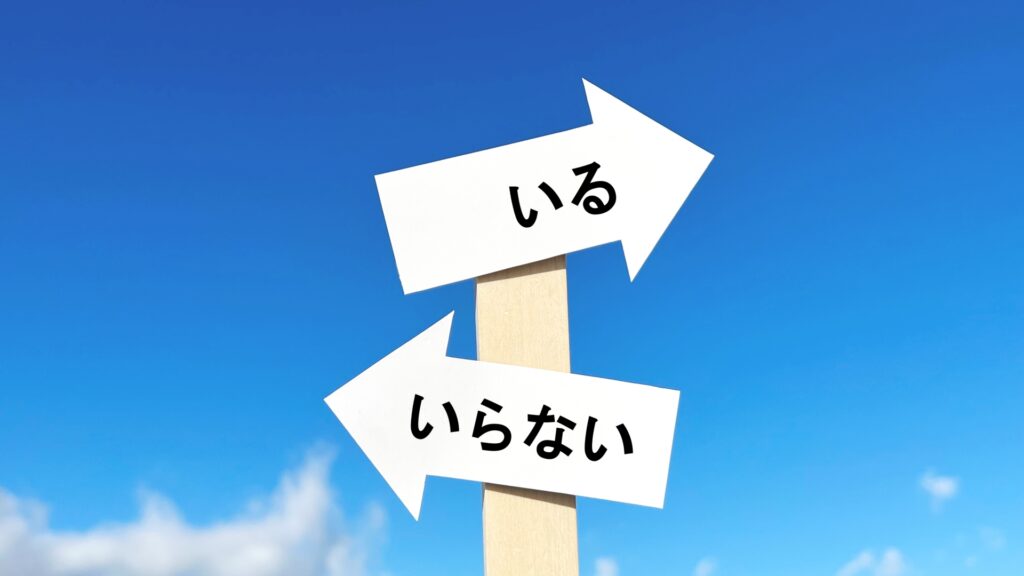
子どもと一緒に「いる・いらない」を仕分けしてみる
「親が勝手に捨てた」となると、子どもは不安や反発を感じてしまいます。
だからこそ、子どもと一緒に“いる・いらない”を判断する時間を持つのが大事。
「このおもちゃ、まだ使ってる?」
「こっちは赤ちゃんの頃のおもちゃだけど、今は使ってないよね?」
会話を通して、“手放す=悪いことじゃない”と伝えられるし、子ども自身も自分で選ぶ力が育っていきます。
大人がリードしつつ、子ども主体で仕分けできる環境をつくることがポイントです。
遊ばなくなったものは「ありがとうしてバイバイ」
感情がこもったおもちゃほど、なかなか手放せないもの。
でも、ただゴミ袋に入れるだけでは、心がついていきませんよね。
我が家では、「このおもちゃ、たくさん遊んだね」「ありがとうって言ってバイバイしようね」と声をかけて、“感謝して手放す”ようにしています。
この“ありがとう”があると、子どもも納得しやすくなるし、物を大切に扱う姿勢も自然と身についていきます。
「季節もの」は一時保管して入れ替え制にする
プール・砂場道具・クリスマス関連グッズなど、“季節限定”で使うおもちゃって意外と多いですよね。
こういったおもちゃは、“常に出しておく”のではなく、オフシーズンには一時的にしまっておく仕組みをつくるとスッキリします。
収納ケースに「夏用」「冬用」などラベルを貼っておけば、入れ替えもしやすく、子どもも「季節感」を学ぶ良いきっかけに。
おもちゃの“定員”を決める
収納スペースには限りがあります。
そこで有効なのが、「この引き出しに入る分だけ」「このカゴに収まる分だけ」と、“定員制ルール”を設けること。
「この箱に入らなかったら、どれかをバイバイしようね」
そう伝えると、子どもも自分で優先順位を考えるようになります。
無限に増えるのを防げるし、子どもの“選ぶ力”も育ちますよ。
「譲る」「寄付する」で“捨てない選択肢”を持つ
「捨てるのはもったいない…」
そんなときにおすすめなのが、“次に使ってくれる人に譲る”という選択肢。
知り合いのママ友に「使えそうだったらどうぞ」と渡したり、寄付団体や子ども向け施設に送ったりすることで、「捨てる」ではなく「活かす」気持ちになれます。
「○○ちゃんがまた使ってくれるって!」と伝えると、子どもも前向きに手放せるようになりますよ。
✔ 今日できること:まずはおもちゃ箱1つだけ“いる・いらない”を仕分けしてみましょう
④おもちゃを減らして気づいたうれしい変化

子どもが「片付けやすくなった」と自分から戻せるように
おもちゃの数が多すぎると、片付けるだけで一苦労。
でも、減らして量を絞ったことで、「子どもが自分からおもちゃを戻すようになった」という変化がありました。
場所が決まっていて、数も少ないと、片付けが“わかりやすく、やりやすく”なるんですよね。
子どもが「自分でできる!」という達成感を得られると、片付けが少しずつ習慣になっていきます。
娘も、最近は『ここは○○のおうちだよね!』と言って自分で戻すようになりました。
自分で選んだおもちゃを大切にするようになった
一緒に仕分けをして「これは残したい」と選んだおもちゃは、子どもにとって“特別”な存在になります。
以前よりもていねいに扱ったり、「これは大事だからここに置く」と自ら保管場所を考えたりするように。
「自分で選んだ」経験が、物への愛着や責任感につながっていくのを感じました。
遊びがシンプルになって、想像力や集中力もアップ
おもちゃが減ると、最初は「遊ぶものが少なくて飽きちゃうかな?」と心配になるかもしれません。
でも実際は、シンプルな遊びの中で想像力がふくらみ、集中力も高まるという変化がありました。
たとえばブロック遊びでは、「決まった作り方」よりも「自分で考える遊び」が増え、工夫やストーリー性が見えてくるように。
“たくさんある”よりも、“厳選された少数精鋭”が、子どもにとっての「楽しい」を引き出してくれることもあるんです。
親も「探す・片付ける」ストレスがぐっと減った
おもちゃの整理が進んだことで、親のストレスも大きく減りました。
「あれどこ?」「あ〜、また踏んだ!」というイライラが少なくなり、片付けにかかる時間も短縮。
家全体のスッキリ感が増して、気持ちにも余裕が生まれるように。
「見た目のごちゃつき=心のモヤモヤ」って、意外とリンクしているんですよね。
あなたのお家では、どのおもちゃが“手放しにくい”と感じますか?
まずは“お気に入りベスト5”を選ぶところから始めてみませんか?
⑤まとめ|少しずつ“おもちゃを選ぶ力”を育てていこう

おもちゃの片付けに悩むママ・パパへ。
「子どものおもちゃが多すぎて、片付かない…」という状況は、誰にとってもよくあることです。
大事なのは、「いきなり全部減らそう」と頑張りすぎないこと。
- 子どもと一緒に“残す”おもちゃを選ぶ
- 小さく始めて、少しずつ習慣にしていく
- 手放すときは「ありがとう」の気持ちを大切にする
- “譲る・保留・入れ替える”など、無理のない方法を選ぶ
そんな小さな工夫の積み重ねが、「片付く空間」と「片付けやすい習慣」をつくっていきます。
そして何より、「子ども自身が“選ぶ力”を育てていける」というのが、一番の収穫かもしれません。
焦らなくて大丈夫。
1日1つのおもちゃでも、「選べた」ことが大きな一歩です。
わが家流の“心地よいおもちゃライフ”、ぜひ一緒に見つけていきましょう。
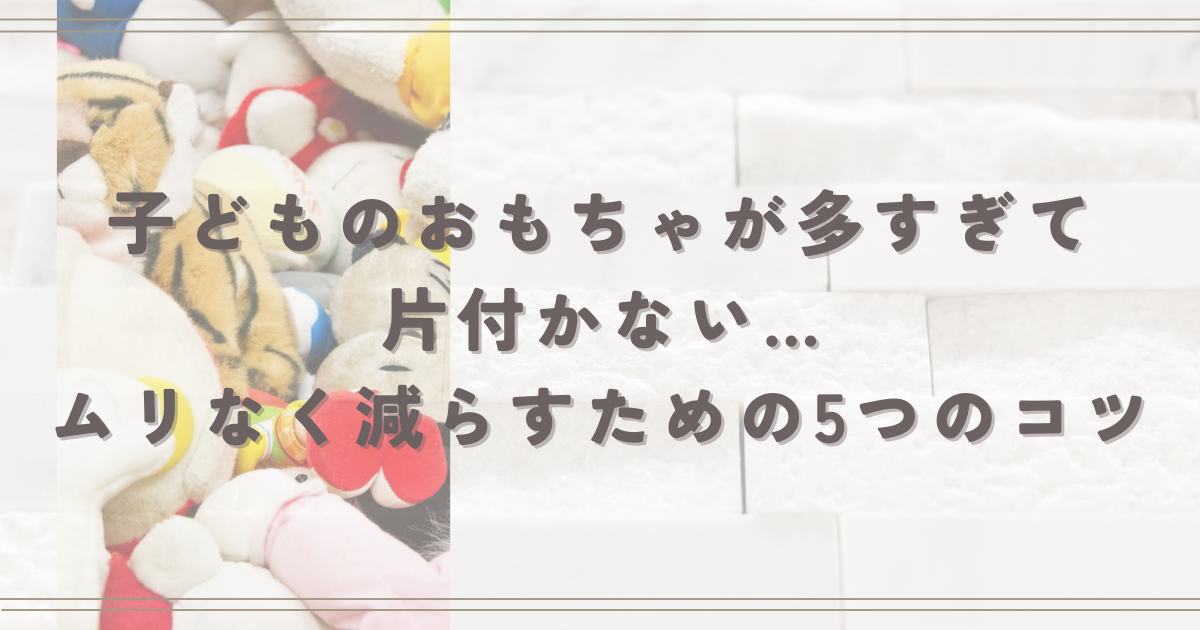
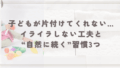
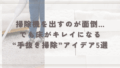
コメント