「せっかく片付けたのに、すぐに元通り…」「収納ボックスに入れたのに、ごちゃごちゃしている…」そんな風に感じることはありませんか?
こんにちは、30代主婦のゆきです。
3歳の娘と暮らす我が家では、毎日使うもの、子どものおもちゃ、書類や日用品…とにかく“物”が多くて、収納しているつもりなのに、気づけばカオス。
片付けても片付けてもスッキリしない毎日に、何度もため息をついていました。
でもある時、「しまいづらさ」こそが“ごちゃつき”の原因だったと気づき、収納の仕組みを少し見直してみたんです。
すると驚くほどラクになって、「私でも続けられる収納」へと変わっていきました。
今回は、ズボラな私でも続けられた収納の工夫と、100均アイテムなど身近なものを使ったアイデアをご紹介します。
見た目の美しさより、「戻しやすさ」を優先することで、ぐっと片付けやすくなりますよ。
① 「収納してもすぐごちゃごちゃ…」の原因は“しまいづらさ”にあった

「しまうのが面倒」は、ズボラの本音
私自身、「片付けよう」と思っても、モノを“しまう”までに手間がかかると途端に面倒になってしまうタイプでした。
たとえば、フタ付きの収納ケース、細かく分類された引き出し、高い位置にある棚——それらに物を戻すのが億劫で、つい近くに置きっぱなしにしてしまっていたんです。
子どもがいると、片付けるタイミングも限られてきますよね。
1日に何度も出し入れするものこそ、“しまいやすい”ことが何より大事なんだと痛感しました。
「定位置があいまい」だと迷う
もう一つの大きな原因は、「ここに戻す」という明確な定位置が決まっていないこと。
なんとなく収納ボックスに入れているだけで、「どこに戻せばいいんだっけ?」と毎回迷ってしまうんです。
たとえば、子どものおもちゃや文房具、日用品など、日々出し入れがあるものほど、「定位置」が決まっていないとごちゃつきやすくなります。
戻す場所に迷うたび、「とりあえずここに置いておこう」が積み重なって、ごちゃごちゃの原因に。
見た目重視の収納は続かない
SNSで見るような“美収納”に憧れて、ラベル付きのケースや統一感のあるグッズをそろえてみたこともありました。
でも、見た目は整っても、使いにくいと感じたら結局続きません。
例えば、「同じカテゴリーのものを1つの箱に入れる」というルールを決めても、箱のサイズや出し入れのしやすさが自分に合っていなければ、どんどん崩れていってしまうんですよね。
私が収納で一番大切だと感じたのは、「とにかくラクなこと」「自分が続けられる仕組み」であること。
それが“ごちゃごちゃ”から卒業するための第一歩でした。
📝「片付けてもすぐ散らかる…」と感じたら、収納だけでなく“物の持ち方”も見直してみませんか?
私が捨てられなかった理由と、少しずつ手放せた方法をまとめた記事はこちら👇
👉 捨てられない私でもできた!物を手放す3つのステップ
② 続かない収納の特徴と、やめた3つの習慣

1. 「とりあえず収納」をやめた
以前の私は、使わない物でも「とりあえずここに入れておこう」と、なんとなく空いているスペースに物を押し込んでいました。
これが積もり積もって、何がどこにあるか分からない“混沌ゾーン”を生む原因に。
今では、「使っていない」「使う予定がない」物は潔く手放す、または別の保管場所に移動するようにしました。
“とりあえず”はごちゃごちゃの元!
2. 「細かすぎる分類」をやめた
細かい分類をすればキレイに見える…と思っていた私。
でも、それが面倒で物を戻せなくなり、結局散らかってしまうことが多かったんです。
今は、「ざっくりでOK」と割り切って、たとえば「子どものお絵かきグッズ」「書類系」「コード類」など、ざっくりしたカテゴリで分けるようにしています。
多少混ざってもストレスにならない収納にしたことで、片付けがラクになりました。
3. 「フタ付き収納」をやめた
一見スッキリ見えるフタ付きボックス。
でも開け閉めが面倒で、結局その上に物を置いたり、別の場所に置きっぱなしになったりしていました。
思いきってフタなしの収納に変えてみたら、出し入れがとてもスムーズに。
よく使う物こそ“ワンアクション”で戻せることが大事だと実感しました。
③ 私が見直してラクになった!収納の5つの工夫

1. よく使う物は「見える収納」に
よく使うアイテムは、見える場所に収納するようにしました。
たとえば子どものおもちゃや日用品などは、透明なケースやオープンラックに入れて“見える化”することで、探す手間も減り、出し入れも簡単に。
2. ラベルは「大まか」でOK
細かいラベリングではなく、「文房具」「おもちゃ」「日用品」など大まかなカテゴリー名だけのラベルにしました。
ざっくり分けることで戻すハードルも低くなり、娘も手伝いやすくなりました。
3. 収納の場所を「動線に合わせる」
使う場所の近くに収納を配置することで、しまい忘れを防止。
たとえばリビングで使うアイテムはリビングの棚に、キッチン用はキッチンに…と、“その場にある”収納がとても便利です。
4. 「引き出しよりカゴ・バスケット」が便利
開け閉めが面倒な引き出しよりも、カゴやバスケットの方がズボラさんには合っていると感じました。
ざっくり入れてもすぐ出せるし、家族みんなが使いやすい。
5. 定期的な「見直し日」を作る
月に1回、収納をチェックする日を設けました。
「あふれてきたかな?」と思ったら、ちょっと見直すだけでリセットできます。
完璧を求めず、気づいたときに“ちょこっと整える”ことが習慣化しました。
④ 100均・家にある物でもできた!ズボラ流・収納見直しアイデア

活用したアイテム①:ダイソーの「仕切りケース」
引き出しの中がすぐごちゃつくので、ダイソーの仕切りケースを使って区切るようにしました。
細かく分けすぎず、ざっくり4区画くらいにすることで、見た目もスッキリ。
活用したアイテム②:家にあった空き箱
靴の空き箱やお菓子の缶などを、収納の“間仕切り”として使っています。
お金をかけなくても、家にあるもので収納がぐっと使いやすくなるのがうれしいポイント。
活用したアイテム③:フック&S字フック
よく使うエコバッグや掃除道具などは、100均のフックやS字フックを使って“引っ掛け収納”に。
扉の内側や冷蔵庫横など、ちょっとしたスペースが便利収納に早変わりします。
ズボラ流の工夫:完璧を求めない
“収納=美しく整っていなければならない”と思いがちですが、ズボラな私にとっては「とにかく使いやすいこと」が最優先。
多少見た目が雑でも、自分が戻せる・使いやすいと思える形を選ぶようにしています。
🔗あわせて読みたい関連記事
・片付けが苦手で床が見えない…私が変われた5つの小さな習慣
→ 小さな片付け習慣を続けることで、散らからない暮らしができた体験談です。
⑤ まとめ|収納は“見た目”より“戻しやすさ”が最優先

収納を見直していく中で、私が一番強く実感したのは、「使いやすさ=戻しやすさ」が整った暮らしにつながるということです。
以前は、片付けてもすぐに散らかってしまい、「自分は整理整頓ができないタイプなんだ」と思い込んでいました。
でも実は、うまくいかない原因は“自分”ではなく、“仕組み”にあったのです。
完璧な収納、美しいラベリング、整然と並んだ棚……それらに憧れながらも続かないことに悩むより、自分にとって「ラク」で「無理なく続けられる」方法を選ぶことが、快適な暮らしをつくる近道でした。
収納は一度見直せば終わり、というものではなく、暮らしの変化に合わせて少しずつ調整していくものだと感じています。
今回ご紹介したズボラ流の工夫が、同じように悩む方にとって、ほんの少しでもヒントになればうれしいです。
“見た目”にとらわれすぎず、“使いやすさ”を大切に。
そんな気楽な収納こそ、毎日を軽やかにしてくれるのだと思います。
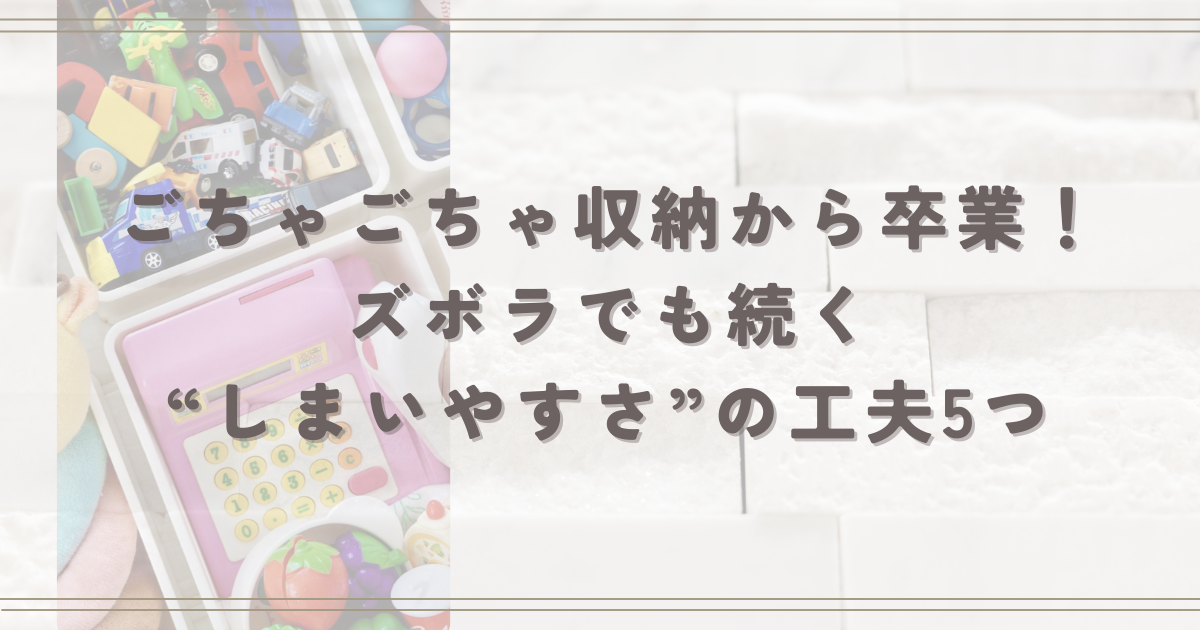
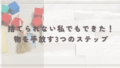
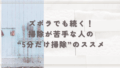
コメント