「もう、なんで片付けてくれないの!?」と毎日のように叫んでいませんか?
子どもに片付けを促すのって、本当に難しいですよね。
何度言っても動かないし、こっちが片付けることになって、イライラがたまるばかり…。
こんにちは、30代主婦のゆきです。
私も以前は、「片付けなさい!」を毎日のように繰り返し、怒ってばかりの日々。
でも怒っても状況は改善せず、親も子もストレスを抱える悪循環に陥っていました。
この記事では、そんな私が試行錯誤の末にたどり着いた「子どもが自然と片付けやすくなる習慣」と「イライラを減らす工夫」を紹介します。
一緒に“頑張りすぎない片付け育児”を目指しませんか?
子どもと片付けでぶつかってばかりのママ・パパに、少しでも心が軽くなるヒントをお届けします。
①子どもに片付けをさせるの、めっちゃ難しい…

片付けなさい!と言っても動かない
子どもに「片付けなさい!」と言っても、全然動いてくれない…そんな経験、ありませんか?
こちらが真剣に言っているのに、子どもは遊び続けたり、「あとで~」とごまかしたり。
ついイラッとして、強く言ってしまうこともありますよね。
でも、よく考えてみると、「片付けなさい」って、子どもにとってはすごく抽象的な言葉なんです。
どこから何をどうすればいいのか、具体的にイメージできないまま「イヤだ」「わからない」になってしまうんですよね。
自分が片付けるしかない日々にイライラ
結局、子どもが動かないと、親が片付けるしかなくなってしまいます。
散らかった部屋を見てため息、寝る前におもちゃを片付けて疲労感…。
「私ばっかりなんで片付けてるの!?」と、不満がつのる日も少なくありません。
私自身、毎晩のようにおもちゃを片付けながら、「これって一体いつまで続くんだろう…」とモヤモヤしていました。
片付けは毎日のことだからこそ、“親が我慢する前提”になってしまうと、本当にストレスなんですよね。
我が家もまさにその状態でした
我が家でも、最初はまさにこの状態でした。
娘が2歳半を過ぎたころ、部屋は毎日おもちゃだらけ。
「片付けて」と言っても無視され、つい怒ってしまい、泣かれる…という悪循環でした。
でもあるとき、「このままじゃずっとつらい」と思い、片付けの教え方をガラッと見直すことに。
すると少しずつ、娘自身が“片付けって楽しいかも”と思えるようになってきたんです。
そんな体験をもとに、次の見出しでは「NGだった声かけ」と「改善のヒント」についてお話しします。
②怒っても逆効果…うまくいかなかった声かけ

「早く片付けて!」と怒っても子どもはやらない
つい言ってしまう「早く片付けて!」という言葉。
でもこれ、実は子どもにとっては「命令」に聞こえてしまい、反発を招くきっかけになるんです。
また、「早く」と言われるとプレッシャーを感じて、やる気がそがれてしまうことも。
子どもはまだ“段取り”をうまく組めないため、「急かされる=怒られてる」としか受け取れないことが多いんですね。
むしろ泣いたり反発したりで、さらに散らかる…
怒っても思うように片付けが進まないばかりか、泣いたり、「イヤ!」と反抗されたり。
そして、片付けるどころかさらにおもちゃをひっくり返して、逆に部屋が大荒れ…なんてこともありますよね。
私も、「これ片付けないと捨てるよ!」と言ってしまったことがあります。
でもそれは、娘にとっては“脅し”と同じ。
信頼関係にもヒビが入りかねないなと反省しました。
親も子もストレスになるだけだった
怒ってばかりの片付けタイムは、親も子もストレスが溜まる一方です。
子どもにとって片付けは“嫌な時間”になり、親も毎回イライラ。
これでは、片付けが「やりたくなること」にはなりません。
だからこそ、無理やりやらせるのではなく、“楽しく導く”方法を見つける必要があるんです。
次の章では、私が実際に取り入れて効果があった「3つの習慣」について紹介します。
③我が家で効果を感じた“片付け習慣”3つの工夫

「タイマー片付けゲーム」:楽しく競争に変える
「片付けしよう!」と言うと渋るのに、「よーいドン!でおもちゃをしまうゲームしよう!」と言うと、なぜか子どもはノリノリになる。
これは我が家で大成功した“片付けゲーム化”のアイデアです。
スマホのタイマーを使って「30秒でどれだけ片付けられるか競争だ!」と声をかけると、まるで遊びの延長のように楽しそうにお片付けを始めます。
カウントダウンが始まると、いつもよりスピードアップしてくれるのも嬉しいポイント。
この方法のコツは、「できた量を褒めること」。
「10個も片付けたんだ!」「すごい早さだったね!」と、とにかく前向きに伝えることで、片付け=楽しいと思ってもらいやすくなります。
「おもちゃの“おうち”を一緒に作る」:定位置がわかりやすく
子どもにとって、「どこにしまえばいいのか」が分からないと、片付けは難しく感じてしまいます。
そこで我が家では、収納場所に“名前”をつけたり、かわいいラベルを貼ったりして、おもちゃの「おうち」を作るようにしました。
たとえば…
- ブロックは「ブロックのへや」
- 絵本は「えほんのおうち」
- 車のおもちゃは「ぶーぶーガレージ」
こうやって“自分専用の収納”を一緒に作ってあげると、子どもにも親しみがわいて、「ここに戻すんだ!」と意識しやすくなるんです。
また、場所がわかりやすいと「ママ、これここでしょ?」と自信を持って行動するようになり、自主性もぐんとアップしました。
「お片付けソング」や声かけの工夫:ポジティブな雰囲気で導く
片付けタイムの雰囲気づくりも、とっても大切です。
私たちは「おかたづけ~おかたづけ~♪」というおなじみの手遊び歌を流しながら、お片付けタイムをスタートさせます。
歌が流れると自然にスイッチが入り、「そろそろおしまいの時間だな」と子ども自身が感じてくれるように。
この“ルーティン”があると、声を荒げることも減りますし、親もラクなんですよね。
また、声かけはなるべくポジティブに。
「あと3分でお片付けしようね」「どっちが早いかな?」など、ワクワクする雰囲気で誘導することがポイントです。
怒るより“誘う”、押しつけるより“楽しむ”。
この空気感づくりが、習慣化の近道になります。
④できない日があってもOK。「できたこと」に目を向ける

片付けができない日=ダメな日ではない
片付け習慣を始めても、毎日うまくいくとは限りません。
「今日は全然やる気がなさそう」「いつもの方法が効かない」…そんな日も、もちろんあります。
でもそれって、“ダメな日”じゃないんです。
大人だって気分が乗らない日があるように、子どもにも「今日は疲れた」「やりたくない」があるのは当たり前。
「できなかった日もあっていい」「今日はママがやってあげる日ね」と、ゆるく受け止めてあげることで、片付けへの印象を悪くしないことが大切です。
小さな「できたね!」を一緒に喜ぶことが継続のカギ
子どもは、できたことを認めてもらうと、とても嬉しそうな表情を見せてくれます。
だから、「1つだけでも片付けられた」「箱に戻せた」といった“小さな成功”を見逃さず、すぐに言葉で伝えるようにしています。
「今、自分でぬいぐるみ戻せたね!すごい!」
「このおもちゃ、ちゃんとおうちに帰ったね~!」
そんなふうに、“一緒に喜ぶ”ことを心がけるだけで、子どもは「やってよかったな」と感じて、また次もやろうという気持ちになってくれます。
褒めるタイミングは、「終わったあと」ではなく、「途中でもOK」。
できた瞬間をパッと拾って、気持ちよく終われるようにすると、継続しやすくなりますよ。
親が無理せず続ける姿を見せることも大事
子どもに片付けを習慣化してもらうには、親が“背中で見せる”こともすごく効果的です。
「今日はママもキッチン片付けようっと」「ここ一緒にキレイにしちゃおうかな」と、あえて声に出して行動することで、「片付けって自然なことなんだな」と伝わります。
とはいえ、親も完璧じゃなくていい。
疲れている日は「ママも疲れちゃったから、今日はちょっとだけね」と伝えるのもアリ。
子どもは、親の“無理しない姿勢”からもたくさんのことを学んでいます。
だからこそ、「ゆるく、でも楽しく続ける」が理想のスタイルなんです。
💡「今日はできなかった…」そんな日も大丈夫。私が“やる気ゼロの日”に助けられた習慣についても書いています👇
👉掃除も片付けも無理…やる気ゼロの日の“ちょっとだけ行動”ルール
⑤まとめ|子どもと一緒に“ゆるく楽しく”が我が家のスタイル

子どもがなかなか片付けてくれないと、つい怒ったり、自分が全部やったりしてしまいがちですよね。
でも、それが続くと、親も子どももどんどん疲れてしまいます。
我が家では、「無理にさせる」ではなく、「一緒にやる」「楽しくやる」ことを大事にして、少しずつ変化が生まれました。
今回ご紹介した3つの習慣――
- タイマーゲームで楽しく競争
- おもちゃのおうち作りで定位置を明確に
- 歌やポジティブな声かけで空気づくり
これらは、どれも“ガミガミ言わずに習慣化する”ための、ちょっとした工夫です。
そして何より大切なのは、できなかった日を責めないこと。
親も子も、無理せず、気楽にやれることから始めていくのが一番です。
片付けは“しつけ”ではなく、“一緒に育てる習慣”。
ゆるく楽しく続けることで、自然と子どもの行動も変わっていきます。
あなたのご家庭にも、ちょっとした工夫で「お片付けができる時間」が増えますように。
完璧じゃなくても大丈夫。
大切なのは、今日より少し気持ちよく過ごせることです。
あなたのお子さんは、どんなときに片付けに前向きになりますか?
「これならできるかも」と思える工夫が、今日からひとつ見つかると嬉しいです。
💡「これならできるかも」と思えたら、こちらの記事もおすすめですよ👇
👉 片付けが苦手で床が見えない…私が変われた5つの小さな習慣
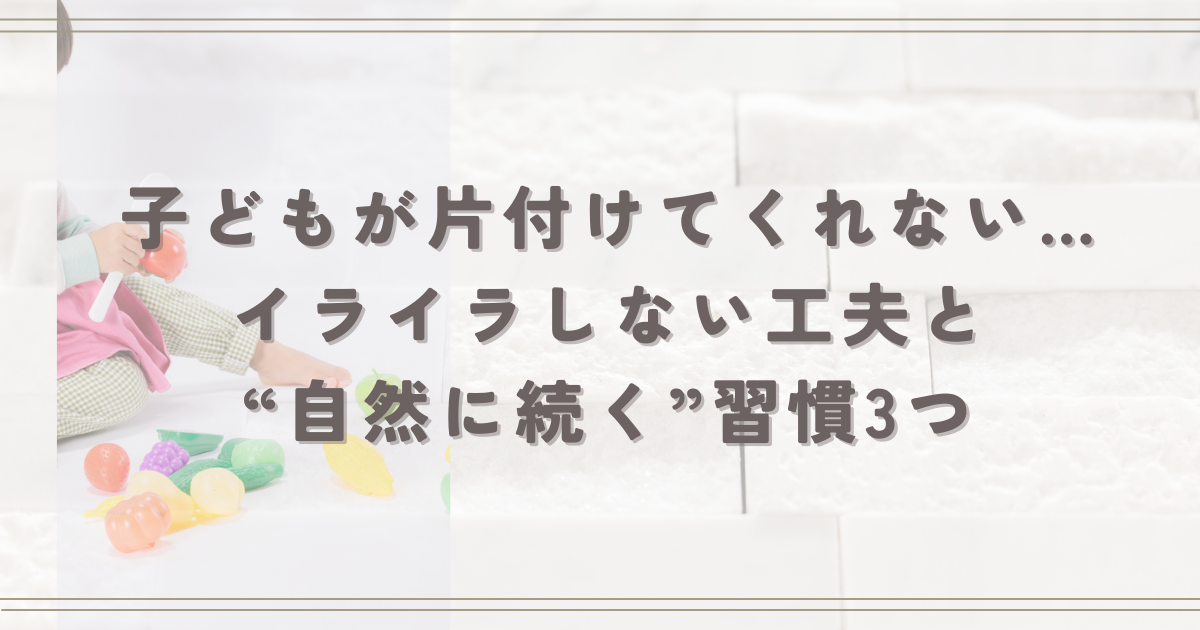
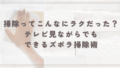
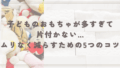
コメント